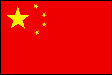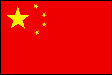中華料理の影に森林減少?
中華料理は火が命
さっと炒める。油通しをする。
時間が勝負といわれる影に燃料不足からの工夫があったとか。
その昔、広大な森林があった中国は、人口の拡大による耕地の拡大や燃料として切られたり、戦争で次々と、森が燃えて減り、燃料不足手前までいってしまいました。
料理するのにも困る羽目になりそうになる手前、石炭という新しい燃料の発見で、中華文明が他のメソポタミアやインダス文明のように消えてしまうことに、ならなかったのですが。
薪の不足をいかに補うか
いかに効率的に料理するか
中国の料理人の知恵が今日の中華料理を築いてきたのです。
|
|
|
| |
|
一人の英雄の虚栄心が森を壊す
文化大革命という名のもと、多くの中国人が、犠牲になった話は有名です。一説には、7000万人もの人々が亡くなったとか。いったい、どのくらいの人が殺されたんだろうか。
文
化大革命前に森林にも悲劇が発生。当時の偉大なる指導者、毛沢東は、世界最大の鉄の生産国になるため、国民に向かって、製鉄を呼びかけます。鍋や農機具ま
でありとあらゆる鉄が、駆り出され鉄を作って、確か、世界最大の生産国になったのか?鉄の生産量が一番わかりやすい指標だったから?
「15年で英国に追いつき、追い越す」
「1959年は鋼鉄の年間生産量を前年の四倍とする」
世間知らずのスローガン
こ
のとき、多くの木が切り倒されました。もちろん鉄を作るための炭として。このときの有名な方法が初歩的な「土法高炉」でも所詮は素人。1958年の大躍進
(本当は大後退)で1959年には破綻。1961年までに2000万人(多分7000万人)があの世へ。多くは、洪水などで農業が出来ず飢え死に。
どれだけ切られたかは分かりません。当時の資料の数値は、一人歩きしているので。
けど、歴史上で一番森をなくした人でしょう。教科書には書かれていない、また書けない話です。多分。書けば、中国や一部から攻撃されますから。
で
も、どうしてそんなバカな話に農民が乗ったのか。それは、共産党が中国を支配した最初の頃。収量が上がり、思いっきり食事が出来たからとか。資本家を追い
出したので分け前が広がっただけなんですけど。でも、農民は党の指導が良かったと信じたんです。鰯の骨も信心からじゃないけど、信用したんです。お陰で、
今では誰も共産党を信じない世の中に。
ちなみに、反対者がいなかったわけではないんです。国防部部長だった彭徳懐元帥。彼は、窮境を訴えた農民に涙を流して謝り、毛沢東を諭そうとしたのですが、失脚。元帥に同調した良心のある人も消えました。
|
畑のまわりに防風林
今、中国では、国を挙げて植林を行っています。
畑の四方をポプラで囲んでいるのです。
防風効果があり、表土が飛ばないようにとのこと
|
|
|
| |
|
忍び寄る危機 From USA
これから中国を襲う危機
それは、松食い虫の被害です。
香港から入ったとか、上海から入ったとか説が分かれるのですが中国のマツを次々に枯らしています。
この松食い虫(というより材線虫)は、日本のと同じとか、ということで、原産はアメリカ。
問題はアメリカ直輸入か、それとも、日本からなのか。今後、大きな問題に発展しなければよいのですが・・
|
結婚にナツメを持参して
古い中国の話(もしかしたら今もあるかも)。結婚する嫁は、相手の親に持参したそうです。一緒に、クリとハシバミも。
ナツメ(Ziziphus
jujuba)は、モモ、スモモ、ウメに続く重要な樹種で、中国の聖樹。強壮の効果や、たくさん実がなるので子孫繁栄を暗示する木です。また、雷が落ちたナツメの木で作った占いの星盤に使うと神さまの考えが分かったとか。
この風習は、朝鮮半島をわたって、日本にも来ているんですね。愛媛県のコーナーで紹介しています
|
|
|
| |
|
お別れにヤナギ
生命力が強いヤナギ。
挿し木にしてもすぐ根付く。そんなこともあってか、中国では霊力のある木という位置づけ
別れの時に、ヤナギの枝を渡していたんです。
ヤナギの元気にあやかって、あちらでも元気でということで。
|
クヌギという木
時代が違うとこうも扱いが違う例
クヌギ、漢字で書くと「櫟」と木に楽しい。古代中国では、野生のサクサン(繭を作る蛾)が繭を作り、絹糸が採れたこと、この絹糸が、衣類の他、楽器の弦に利用
また実は、大切な食べ物(狩猟採集の時代)
生きる上で楽しませてくれるという有り難い木でした。
そんなこともあって、信仰の対象になっていたとか
しかし、時代が進み、荘子の時代。農業が発達し、栽培した食料が得られるようになってからは、可哀想な扱いに・・・・・
木材として利用するには、ダメな木ということで「無用の木」と呼ばれたそうです。柱は虫に食われ、船に使うと沈むし、棺桶は早く腐る役立たずの木と罵らせたそうです。
「樗櫟の材(ちょれきのざい)」みたいな奴と呼ばれないようにがんばりましょう。
|
|
|

向こうのまな板です。切っているのはバナナの花
(イチョウの保証はなし)
|
|
中華料理を支えるイチョウ
中華料理の材料を刻むのに必要なまな板
日本では、ヒノキやアスナロが重宝されますが中国ではイチョウ
しかし、中国のまな板は長方形ではなく木の輪切り。(普通の家では、日本と一緒の長方形とか)
中華料理で一番いいまな板はイチョウの材だとか辺材も心材の淡黄色で年輪が目立たないのが特徴です。
ちゃんとした中華料理屋ではイチョウのまな板を使っているのでしょうかね
|
ボケの酒は美人の元
ボケの実をつけた酒
ボケ酒
クエン酸、酒石酸、リンゴ酸が豊富
疲労回復や整腸作用に効用があるとか
しかも、絶世の美人?である楊貴妃が好んでいたらしいのです。美しさを保つにはいいお酒かもしれません。
ちなみに、生食は不可とか
|
|
|
| |
|
お茶を飲んだ最初の人
茶経の陸羽によれば、最初にお茶を飲んだのは神農とか。人類に火の使用、農耕技術を教えたと言われる超人(宇宙人?)
一日に100種類の野草を食べて72種類の毒草に当たり、お茶で消毒して事なきを得たそうです。
何
故お茶を飲んだかというと、木陰でお湯を飲んでいた時に、葉っぱがひょろりと湯の中に。するといい香りが立ちこめ、味も良いということで飲むきっかけに
なったとか。お茶の木の原産は、四川省、雲南省、貴州省にまたがる山岳地帯ともいわれています。紀元前2700年以前のこととか。
実在の人では周の公旦という話です。
三国志の前の時代、前漢(紀元前100年頃)にはお茶の存在は中国でも知られていて、貴重なモノとして扱われていたそうです。
唐の時代では、餅茶(ピンチャ)という茶葉を押し固めたモノをベースに、ネギや生姜を加える雑茶という方法で飲んでいたそうです。このころ茶店も出現して一般的に飲まれるようになったそうです。
|